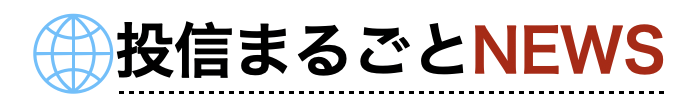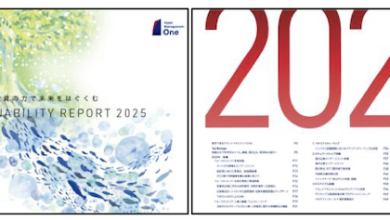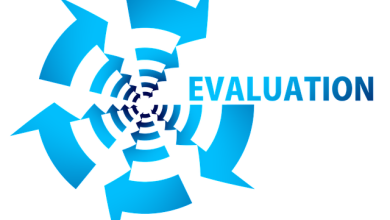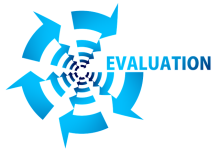2025年6月13日に年金制度改正法(正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立しました。同改正法は、社会経済の変化に対応し、持続可能な年金制度を構築するための多岐にわたる内容を含んでいます。主なポイントは以下の通りです。
1. 被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大
- 「106万円の壁」の撤廃・賃金要件の廃止:
- これまで月額8.8万円(年収106万円相当)以上の賃金要件を満たした短時間労働者が対象でしたが、この賃金要件が公布から3年以内に撤廃されます。これにより、週20時間以上などの就業条件を満たせば、賃金にかかわらず社会保険の加入対象となります。低所得の非正規労働者の老後保障の拡充が期待されます。
- 企業規模要件の段階的撤廃:
- 現在51人以上の企業が対象となっている適用要件が、段階的に撤廃されます(令和9年10月~令和17年10月にかけて)。最終的には、企業規模にかかわらず、短時間労働者も厚生年金・健康保険に加入できるようになります。
- 個人事業所の非適用業種の解消:
- これまで社会保険の適用対象外であった、常時5人以上を雇用する個人事業所(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業等)が、適用事業所となります(令和11年10月施行)。
2. 在職老齢年金制度の見直し
- 年金支給停止基準額の引き上げ:
- 働きながら年金を受給する際の年金支給停止基準が、現行の「年金(基本月額)と給与(総報酬月額相当額)を足して50万円」を超えたら年金がカットされる仕組みから、段階的に「62万円」「71万円」に引き上げられます(令和8年4月施行)。これにより、働きながら年金を受け取りやすくなり、就労意欲の向上が期待されます。
3. 遺族年金の見直し
- 男女間の受給条件の差の解消:
- これまで男女で異なっていた支給条件が見直され、男女差が解消されます。
- 男女ともに受給しやすくなり、原則5年間の有期給付となりますが、低所得など配慮が必要な場合は最長65歳まで所得に応じた給付継続が可能です。
- 女性のみに適用されていた加算が段階的に廃止されます(25年かけて段階的に縮小)。
- 遺族厚生年金の受給権者の老齢年金繰下げ申し出の容認:
- 遺族厚生年金を受けている場合でも、老齢基礎年金・老齢厚生年金(遺族厚生年金を請求していない場合に限る)の繰下げ申し出が可能になります(令和10年4月1日施行)。
- 離婚時の年金分割請求期限の延長:
- 離婚時の年金分割の請求期限が2年から5年に延長されます(公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日施行)。
4. 厚生年金保険の標準報酬月額上限の引き上げ
- 上限額の段階的引き上げ:
- 厚生年金保険料や年金額の計算に使う「標準報酬月額」の上限(現行65万円)が、3年間かけて段階的に75万円まで引き上げられます(令和9年9月以降順次施行)。これにより、高所得者の保険料が増加しますが、将来の年金受給額も増えることになります。
5. 私的年金制度(iDeCo)の見直し
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の引き上げ:
- iDeCoの加入可能年齢が65歳未満から70歳未満に引き上げられます。
6. 基礎年金の給付水準の底上げ
- 将来的な基礎年金の給付水準の底上げについて、次期財政検証(4年後)の結果を踏まえて必要な法制上の措置を講じるとされています。具体的な給付水準の底上げ方法については、今後の検討となります。
これらの改正は、少子高齢化が進む中で、多様な働き方に対応し、年金制度の持続可能性と公平性を高めることを目指しています。施行時期は項目によって異なりますので、ご自身の状況に合わせて確認することが重要です。
→年金制度改革法の詳細(厚生労働省)